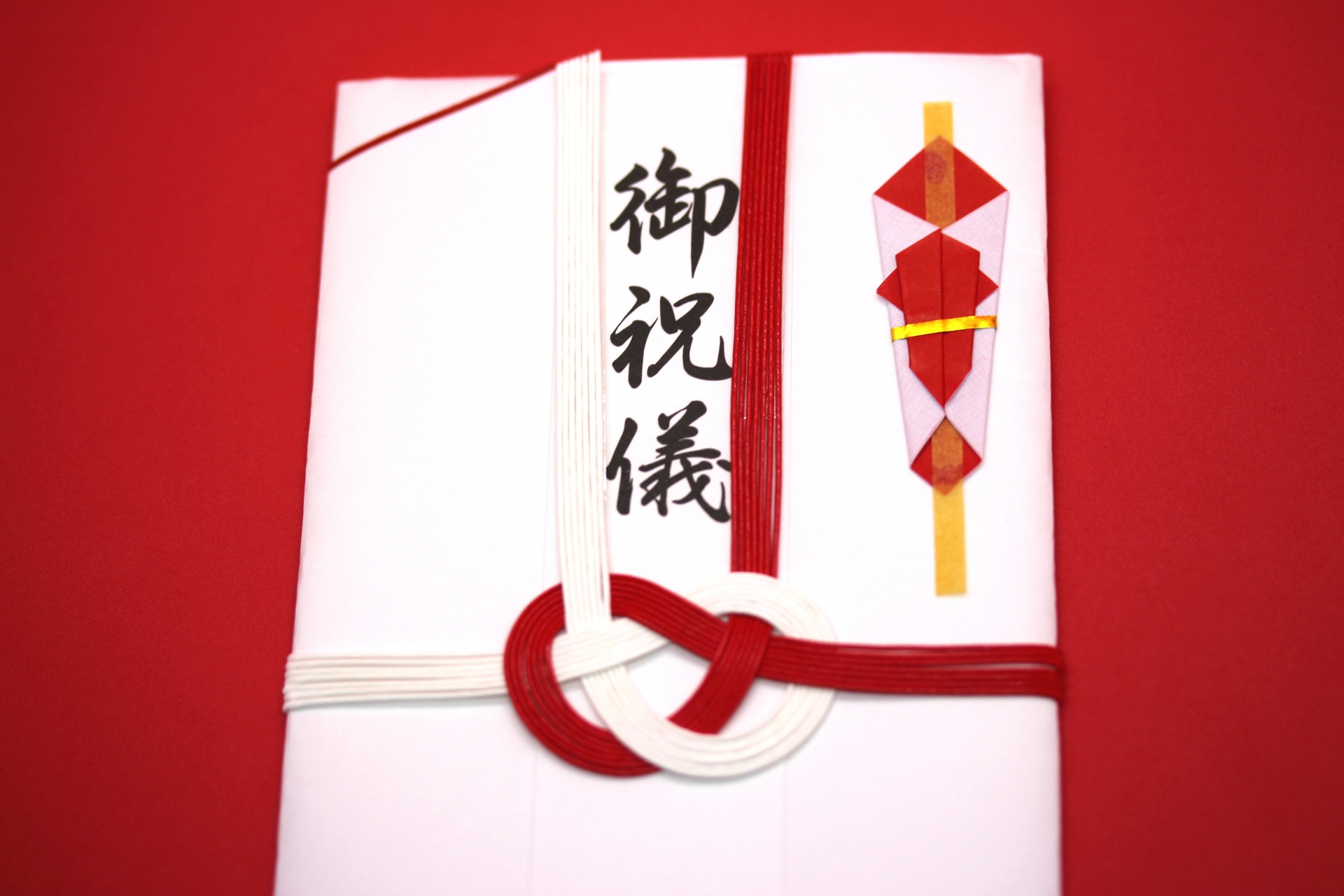ニット帽やベレー帽や麦わら帽子など女性のファッションのトータルコーディネートには欠かせないアイテムの帽子ですが、室内に入った時帽子はどうしていますか?
室内に入ったら「帽子は脱ぎなさい」と言われた人も多いかと思いますが、帽子を脱いだら髪がぺったんこなので、脱ぎたくないという女性は多いですよね。
室内に入ったら男性は帽子を脱ぐのがマナーとされていますが、女性の場合はどうなのでしょう?
室内や食事や映画の場合など、それぞれのシーン別でみてみましょう。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-
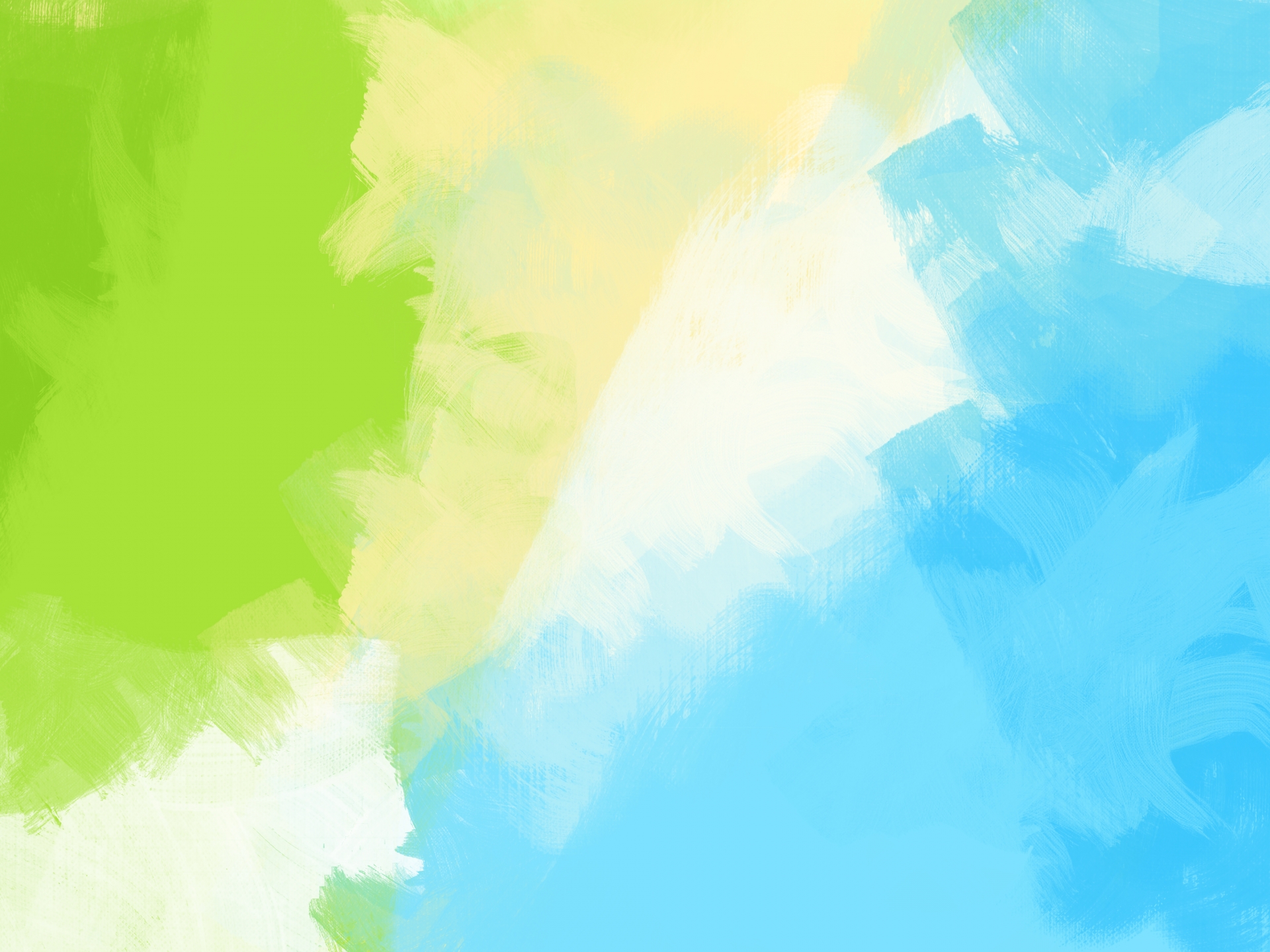
-
アクリル絵の具は洗濯してもOK!布に描くことが可能なアイテム
アクリル絵の具を使って布に描くとき、「洗濯をしてもアクリル絵の具は落ちない」という話を聞いたことがあ...
-

-
お守りを落としたことの意味とは?モノが持つエネルギーについて
お守りを落とした! バチが当たってしまいそうで、ビクビクしてしまいますが、お守りが自分の身代わりに...
スポンサーリンク
まずは男性と女性の帽子のマナーについて知っておきましょう
日よけやオシャレのために被る帽子は、いくつか持っている人も多いのではないでしょうか。
帽子はとても便利なファッションアイテムですが、被る際には守るべきマナーが存在します。
帽子は装いの一部を飾る物ですが、中にはカジュアルなキャップスタイルの帽子などもあります。
そして、男性と女性の帽子には着用シーンにいくつかの違いがあります。
男性が被ることの多いキャップは、屋内では基本的にとらなくてはいけないものです。
女性も同様の考え方で、日よけの麦わら帽子や、キャップを被る場合は、屋内では取るべきと考えられます。
その他の帽子は、基本的には屋内であってもかぶったままでも良いとされています。
ただし、男性は基本的にはどんな帽子であっても屋内では帽子はとるのがマナーとされています。
また、人と挨拶をする時には帽子を被っていたらとるのが礼儀ですが、これは実は男性だけに適用するマナーなのです。
他にも食事をしている時や、国歌が流れている時なども女性の帽子は取らなくても良いですが、男性はとらなくてはいけないということになります。
ただし、女性の場合、つばが広いなどで他人に迷惑がかかるような時は、状況判断して取るのが礼儀と言えるでしょう。
女性の帽子のマナーやエチケットをシーン別でみてみましょう
帽子は、装いに華を添えてくれるファッションアイテムでもあります。
帽子の歴史が深い欧米では、室内でも靴を履いて過ごすことが一般的ですよね。
欧米では、帽子は靴を履いている時はそのままで良いというスタンダードな考え方が浸透しています。
つまり、帽子はトータルコーディネートの一部であるということから、部屋で帽子を取らなくても良いのです。
ただし、室内では大きなブリムハットや、つばの大きな日よけ帽子は避け、ターバンやニット帽などがリラックスできるため、おすすめです。
会食の席などあらたまった席では、帽子はとるべきなのか悩むこともありますね。
男性は、どんな帽子であっても室内では必ずとるのがマナーです。
女性はというと、着ている装いに合わせた小さめな帽子であればとらなくてもマナー違反にはなりません。
観劇や映画館では、勝負帽子で装いに合わせた華やかな帽子をチョイスしたところですよね。
個性が強めの帽子でも場を華やかにしてくれるので、帽子が似合うシチュエーションとも言えます。
ただし、席に座って鑑賞する場合は、後ろの方の視界を邪魔していないかということに注意を払う必要があります。
そのような細やかな気遣いをしてこそ、帽子マスターと言えるのではないでしょうか。
帽子をかぶるようになったのはいつ?女性の帽子の歴史やマナーについて
帽子の歴史を紐解いていくと、紀元前4000年の古代エジプト時代にまでさかのぼります。
この時代では、王が冠を被り、市民は頭巾を被っていた痕跡があることから、すでにこのころから被り物は存在していたと考えられます。
日本では、神代紀(じんだいき)の作笠(かさぬい)が始まりと言われています。
また、弥生時代の埴輪(はにわ)にも帽子風の装飾が見られるということから、帽子の前身のものがこの時代からすでにあったとも考えられます。
日本の偉人として有名な「聖徳太子」は、冠を被っている記録が残っていますが、これは日本に仏教が伝わってくると同時に、中国から入ってきたと考えられています。
古事記や日本書紀にも、「冠」や「笠」といった単語があることからも、この時代には日本にも帽子が伝わってきたのでしょう。
やがて、平安朝時代になると、被り物がそれぞれの身分階級を表す物になります。
素材が、麻や絹のような高級品で作られた物は身分の高い者が身に付け、庶民は木綿で作られた者というように、帽子が地位を表す重要な物だったのです。
時代の移り変わりと共に、帽子も形を変えていきます。
紙を漆で塗り固めて作る鳥帽子から始まり、笠、頭巾などが広がります。
江戸時代に入る頃には、このような被り物も種類を増やしながら、実用性やオシャレさも兼ね備えつつ、これが現代にもつながっているのです。
室内では女性も帽子を脱ぐのがマナー?みんなはどうしてる?
男性の帽子は、基本的には屋内ではとるのがマナーとされていますが、このような背景には「帽子は外の汚れをよけてくれるもの」という考えから、屋内で帽子を被ることでその汚れを持ち込む、つまり相手がいる場合は失礼にあたるからなのです。
女性の帽子の多くは、コーディネートの一部として認められているため、屋内であっても基本的にほとんどの場所で帽子はとらなくてもマナー違反にはあたりません。
しかし、親や周りの大人から「室内では帽子をとりなさい」としつけられてきた人は食事の場で帽子をつけたまま食事するということに抵抗がある人もいます。
靴を履いたままお茶をするカフェやレストランでは帽子はとらないという人も多いようです。
コートを脱ぎ、靴も脱ぐような場所での食事では帽子もとるという意見もありました。
時と場所を見極めて、場面に応じて帽子をとるかの判断をするということが良いのではないでしょうか。
帽子のマナーは相手を不快にさせない事が大事!
帽子のマナーといえど、人によっては違う見識の人もいるでしょう。
年代によっても考え方は違います。
今の年配の方たちは、室内では帽子をとるということが常識でしたし、そのように親からもしつけられてきたということがあります。
時代が変わるとともに、考え方も変わってきており、多様化している今、帽子のマナーも時と場合により変わるものと言えるでしょう。
例えば、病気の治療などで止む無くウィッグや帽子を付けて過ごさなくてはいけない人もいます。
このような人は、帽子を被ることで、頭皮が守られ抜け毛を防げるというメリットも多いでしょう。
マナーとは、どのような場合であっても相手を不快にさせないということが前提です。
TPOをわきまえて、適した判断をするということが大切です。