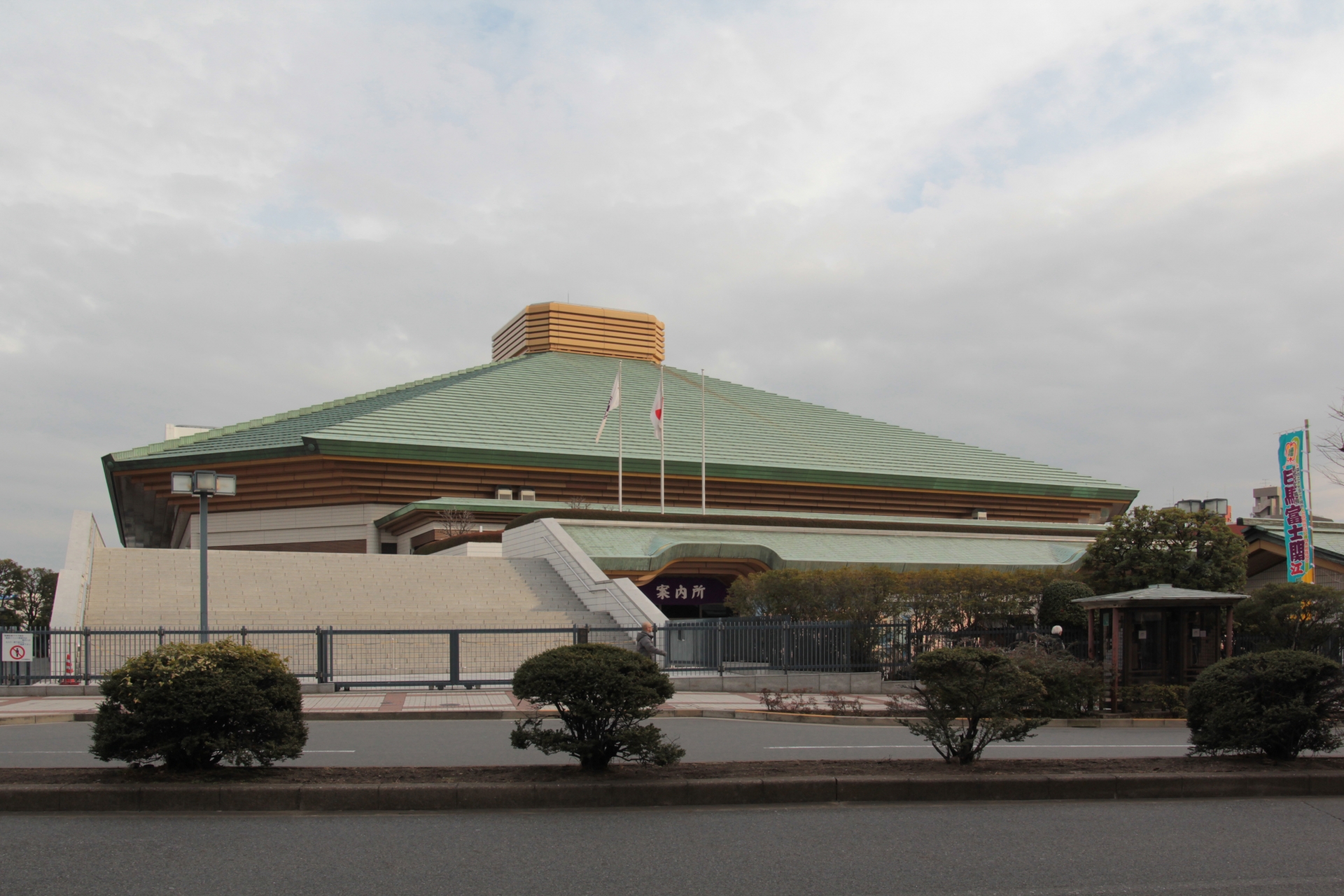少年野球の指導者にとって、低学年の子供たちに飽きないように野球を教えるのは大変なこと。
どんな練習をさせればやる気を出してやってもらえるのか、まずは基礎練習からさせた方がいいのか頭を悩ませているのではないでしょうか?
そんな人たちのために、低学年の子供に対する少年野球の指導方法と練習メニューについて説明します。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
スポンサーリンク
少年野球で低学年を指導する上で大切なこととは?
少年野球で低学年の子供達に教える場合の大切なポイント
野球の楽しさを知ってもらう
「野球が好き」という気持ちは同じでも、中学・高校と学年が上がると、より厳しい練習も必要になるでしょう。
しかし、まず野球に触れ、野球を楽しいと感じてもらうことが大切です。幼い頃は、ボールが一つあるだけで、投げたり転がしたり追いかけたり。
そんな楽しい気持ちで野球に接することが、まず何より大切なことです。
低学年は「基本の動き」が重要
野球には、基本となる動作があります。「走る・投げる・打つ・捕る」という動作が野球の基本です。
低学年の子どもたちでは、ボールを正確に投げる・捕ることや、遠くに投げることは体格的にも難しいでしょう。
ただ、この時期に身についた投げ方や取り方におかしな癖があると、高学年になってから修正しようとしても時間がかかったり、なかなか直せないこともあります。
高学年になっても野球を続けていくためには投げ方、捕り方など「○○方」を重視し、基本を大切に指導するようにしましょう。
少年野球の指導法!低学年は基礎練習をしっかりと!
少年野球の練習では、低学年の子供に対して重点的に基礎練習を行いましょう。
キャッチボールができなければ高学年と一緒に練習したり、一連のプレーもできません。キャッチボール中に暴投してしまい、ボールが遠くに転がってしまったときは、受け手だけでなく投げた子どもも一緒に捕りに行かせます。
ベース間のキャッチボールでも、暴投で抜けた場合はキャッチボールに参加しているみんなで追いかけるようにします。
自分がきちんとやらないと、一緒に練習しているみんなにも迷惑がかかることがわかれば、送球も丁寧にするよう心がけるようになります。
なかには「より上手くなりたい」という気持ちよりも、ただ「野球がやりたい」「好きだから野球をする」という子もいるでしょう。
そんな子どもに向上心を持ってもらうためには、ときどき試合形式での練習を組み込みましょう。
試合形式で練習するとプレー全体の流れや、適度な緊張感が経験できます。勝敗がつくことで、より「勝ちたい、上達したい」という気持ちも刺激します。
少年野球で低学年を指導する時、こんな練習方法を取り入れてみよう!
練習のスタートは鬼ごっこもおすすめ
低学年では集中力に不安があったり、練習の開始時にダラダラしてやる気のスイッチが入らないことがあります。
そんなときは、鬼ごっこや警ドロなど走り回る遊びで走り回り、練習へのモチベーションを上げます。
仲間との競い合いで向上心を刺激
ボールを遠くに投げる遠投は、単純ですがそれぞれのフォームの確認もでき、子どもたちの向上心を刺激する練習になります。
キャッチボールで投げるときの投球フォームで、一番遠くへ投げられるのは誰かを競います。このとき、下半身を使って正しいフォームで投げられているかチェックできます。
ただし、軽いキャッチボールで肩をならしてから行ってください。いきなりの遠投は肩を痛める原因になります。
どのくらいの距離かという単純さが、逆に子どもたちの競争心を刺激して「もっと遠くに投げられるようになりたい」という向上心に繋がります。
フライが苦手な低学年の子にはどんな練習方法がおすすめ?
フライの捕球は基礎的な技術ですが、野球を始めたばかりの低学年の子どもにとっては上から落ちてくるボールに恐怖感を抱き、上手く捕れないことがあります。
フライの捕球には「おでこキャッチ」をしてみましょう。
- おでこキャッチ
グローブを顔の横、おでこのあたりにつけて構え、グローブは動かさずに体をボールの落下地点に移動させて捕球します。
フライがうまく捕れない理由として次のようなことがあるからです。
- 走りながら腕を突き出してグローブを出してしまい、落下地点に間に合わない
- 万歳のように両手を上げて上を見すぎると、ボールが落下する地点を正しく予測できない
- ボールを捕ろうと動作に焦ってボールの落下地点に素早く移動できない
これらを克服するために「おでこキャッチ」の練習が効果的です。
慣れてくると、ついついグローブを突き出す癖を直して目的の地点に素早く移動し、顔を上げすぎずに捕球することができるようになるでしょう。
この練習では体の動きや姿勢を制限するため、逆に空間認知力が磨かれます。
少年野球の指導者が注意すべきポイントとは?
低学年の子どもに野球を指導する場合、注意したいのは体のつくりと練習量です。
体力的にはもちろんですが、骨格や関節も成長途中で柔らかいため練習のし過ぎはケガに繋がります。
全力での投球数は、学年によって1日の球数を制限しましょう。
- 高学年…100球
- 中学年…80球
- 低学年…50球
少年野球では、飛びぬけて優れた選手が現れることがあります。特にピッチャーでは、毎試合の投球が求められ、結果的にケガや故障を引き起こすことがあるのです。
ピッチャーは3人でも回すことは可能ですが、できれば4人は育てておきたいところです。
運動神経は9~11歳の頃に最も良くなるとされ「ゴールデンエイジ」という呼び名もあります。
その前後も、3~8歳は「プレゴールデンエイジ」、12~14歳を「ポストゴールデンエイジ」というスポーツの上達には非常に重要な時期です。
技術面がぐんぐん向上する時期でもあり、技術的なトレーニングを重視するといいでしょう。
筋力や持久力は中学・高校生以降に発達するので、小学生には長距離ランニングや負荷の強い筋肉トレーニングをしても無意味です。
子供の成長にあった練習をすることが必要なのです。