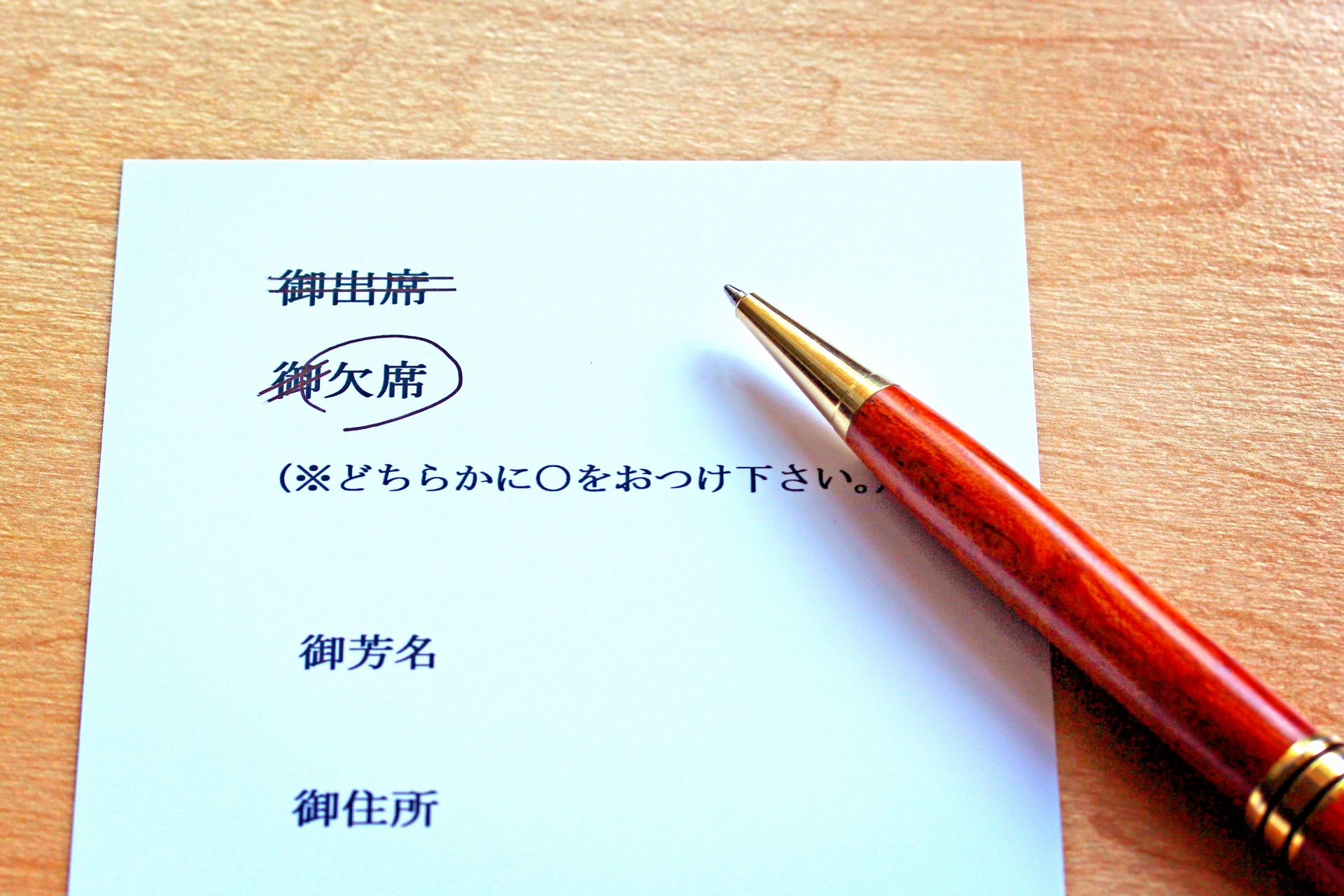算数ができない子供、算数が得意な子ども。
この2つの差ってなんだと思いますか?
それは、算数の、数字の概念を理解しているかしていないかの差なのです。
そして、文章を読み解く力があるかどうかです。
文章問題を理解しないと、どの計算が求められているのかがわからないですよね?
算数は、生活に密着しています。
勉強ではなく、日常生活に取り入れながら数字の概念が理解できるよう導いてあげましょうね!
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-
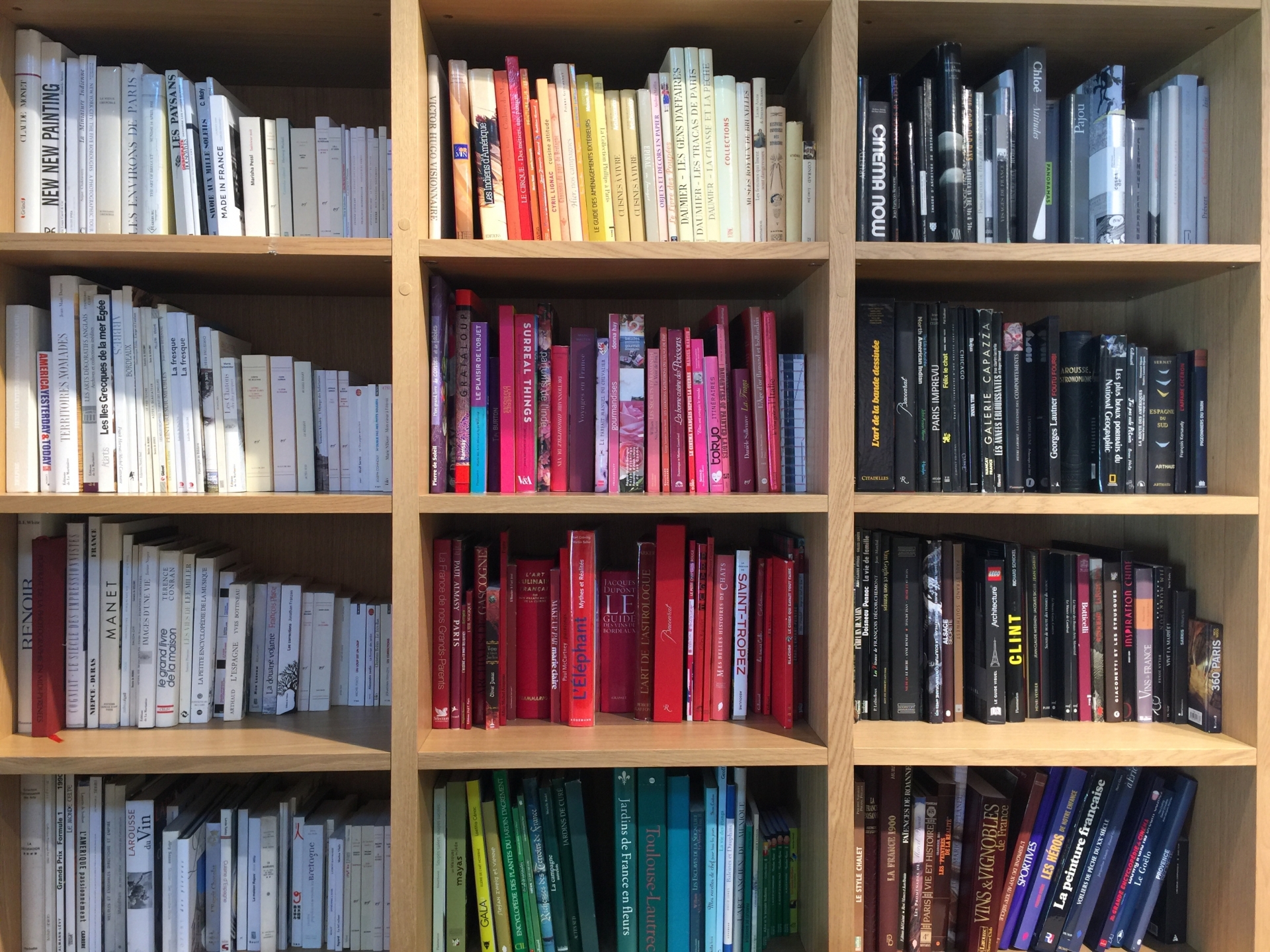
-
本棚をきれいに見せる収納アイデアをご紹介!グッズを活用しよう
リビングに本棚があると、なんでも入れて収納してしまうのでぐちゃぐちゃになってしまっていませんか。 ...
-

-
赤ちゃんが母親になつかないのはなぜ?接し方を変えてみましょう
赤ちゃんが生まれて毎日忙しい新米ママ。しかし、母親である自分になつかないと感じるママも多いといいます...
-

-
春の花壇の作り方や植えたい花や、初心者でも簡単人気の花を紹介
色とりどりの花が咲き誇った花壇はステキですね! 春になったらガーデニングの準備を始める人、これから...
-

-
ペットボトルを凍らせるとクーラーの代わりになるの?除湿効果も
暑い夏、クーラーがない部屋で快適に過ごすにはどうしたら良いか、頭を悩ませている人もいますよね。ペット...
-
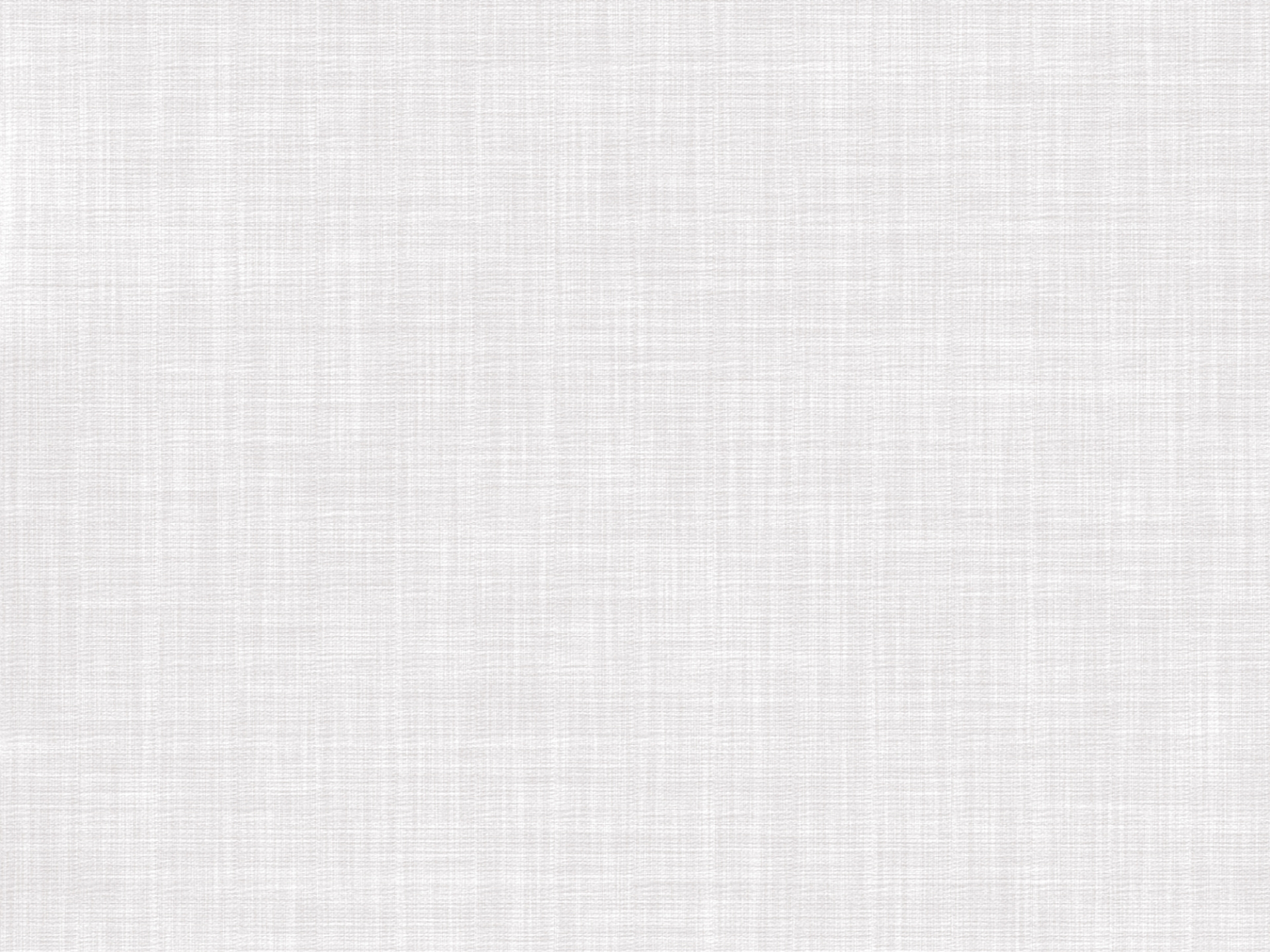
-
布を購入するときのサイズは何センチから?お店によって違います
布を購入するときにはどのくらいのサイズから買うことができるのでしょうか?私はずっと1メートルからしか...
スポンサーリンク
算数ができないウチの子供!計算ができないのではなく「文章」が理解できないのでは?
うちの子は算数が出来ないと嘆いているをよく耳にします。
ところで、算数で出来ていないのはどの部分なのでしょう?
もし、文章問題の時に出来てない事が多いなら、それは算数が出来ないのではなく、問題を理解できていない可能性があります。
どちらかというと、国語の問題になります。
文章は読めると思います。
しかし、その内容がどういうことなのかがわかっていない状態です。
その為、和文和訳が必要になってきます。
もし、ご家庭で教えるとしたら、まずは文章問題を呼んでもらい、「どういうことを聞いているの?」と質問してみましょう。
「わからない」なら質問の意味を理解していないということなので、まずは文章問題の和訳をする事から始めましょう。
算数ができない子供はいない!算数も運動のように訓練が必要です!
算数には基本的な計算力が必要です。
躓きやすいのはかけ算・わり算が出てくる時期です。
文章問題や応用力なども大事ですが、まずは基本の計算力です。
いくらテクニックを磨いても、基本が出来ていないと伸びません。スポーツでも一緒ですよね。
単純な計算は繰り返し行なうことで、必ず出来るようになりますし、スピードも上がってきます。
ご家庭で行う場合はシンプルな計算ドリルなどを用意しましょう。
それを毎日1ページで良いので解いていきます。
そして必ず丸付けをして、間違っていた問題はやり直します。
少々手間がかかりますが、丸付けは子供ではなく親がしましょう。
子供が自分でやると、褒められたいので採点が甘くなる可能性がありますし、親が丸付けすることで、子供の苦手な部分を知ることも出来ます。
算数ができない子供は、算数の概念を理解していないことが多い
算数が出来ない子の中には、数の概念を理解できていない事があります。
1から100まで数えられるようになったからと言って、それは数を理解したわけではありません。
歌を覚えるのと一緒で、言葉を覚えたのです。
そこで、この子はもう数が数えられると、計算ドリルで計算式などを教えてゆくと、それなりに解けるようにはなります。
けれど、のちのち簡単なことで躓くことになるのです。
ある女の子は三角形の面積を求める問題で、「7×7÷2=245」と回答しました。
大人から見ると答えの数が大きすぎるので、「小数点を忘れたのかな?」と思いますよね?
そこで「何か忘れてない?」と聞いてみても、「???」という顔をします。
彼女は割られる数よりも答えが大きい数であることに違和感を抱いていないのです。
割り算というのは等分することなので、元の数より絶対に小さくなりますよね?
そのイメージが出来ていないということです。
数というのは数を数えられることから始まり、大きい・小さい・同じ、1対1の比較、数を等分すること、そして1対多数での比較と多くの概念があります。
それは日常生活で習得することが可能なものばかりです。
例えば、誕生日ケーキを人数分に切り分ければそれは数の等分で割り算の考え方に繋がります。
お話に出てきた3匹のウサギの耳の数を「ウサギには耳が2つ、3匹いるから全部で耳はいくつ?」という話をすれば、1対多数の比較になり、つまり掛け算の考え方に繋がるのです。
ぜひ、日常の中で数を体感して欲しいなと思います。
計算はさせない。日常の中に計算や数字を取り入れる。
算数が出来ない子は、すでに苦手意識が芽生えてしまっています。
まずはそれを取り除くことから、始めましょう。
毎日触れていると、どんなものでも抵抗感が薄れていきますよね。
例えば、毎日お手伝いする子の中には、小さな頃からの習慣で全く抵抗なく「当たり前」として行なっている子がいます。
でも、今まで全く何もせず親が全てをしてあげていたような子に、「○○しといて」とお手伝いをお願いしても、きっとかなり文句を言うかやらないでしょう。
数字も同じで、ずっと身近にあれば、苦手な意識も抵抗感も薄れるのです。
数字に苦手意識や抵抗感があって、さらに数の概念もあまり理解していないのに、計算ドリルをいきなり渡されたら、それはもうかなりの苦行でしょう。
ドリルを開いて数字を目にした瞬間に、嫌悪感すら抱いているかもしれません。
数というのは日常のそこかしこに存在します。
買い物の最中や家族でおやつを分けるとき、数は身近なところにたくさんあるのです。
まずは、それに気付かせることから始めるのが良いでしょう。
数字は無限。この概念を知ることができれば、算数が好きになる!
数というのはゼロを基点にプラスにもマイナスにも無限に続いています。
それらを、計算するためのルールが計算式です。
足し算・引き算に始まり、掛け算・割り算と計算式はどんどん増えてゆきますよね。
それは全てが計算のルールです。
そして難しくなればなるほど、数の概念を理解していないと、計算式を見てもどうしていう式になるのか理解できないので、だんだんと算数が出来なくなっていきます。
出来なくなると、嫌いになってしまいますよね。
意味のわからないものを漠然と覚えるというのは、意外に辛い作業です。
算数で最も重要なのは算数の概念です。
数は連続して続いているもので、数と数をまとめると増える、ある数からある数を除くと減るといった、基本的な概念です。
重さや速さといったものも体感として感じる事ができれば、算数はずっと簡単になるものです。